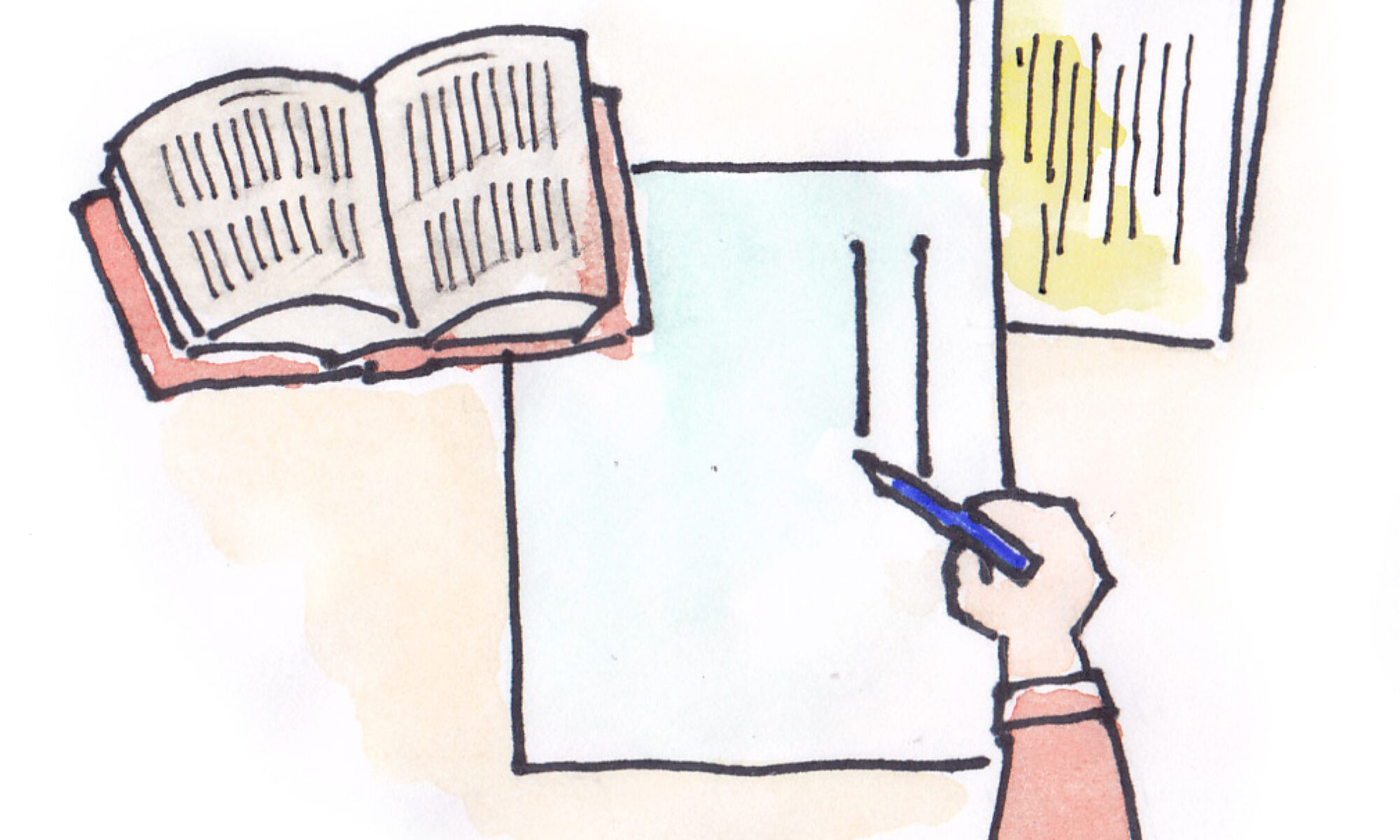あなたの思い、お寄せください
あなたの心の中にある思い。
言葉にして初めて気づくことがあります。
ぜひ、お聞かせください。
投稿フォーム>>
塩谷達也の「Spirit of Gospel」
We shall overcome,we shall overcome
We shall overcome some day
Oh deep in my heart, I do believe
That we shall overcome some day
#42
そして、賛美の歌を歌ってから、みなオリーブ山へ出かけて行った。
新約聖書 マタイの福音書26章30節
イエスと弟子たちとの最後の晩餐のすぐ後に、こう書かれているんですね。 賛美の歌―ゴスペルを共に歌ったと。そしてその後、イエスは弟子たちにこう話すんです。
「あなたがたはみな、今夜、わたしのゆえにつまずきます。」
この重い言葉を言う前に、みんなで賛美の歌を歌ったと。 さらっと書いてありますけれども、本当にイエスはこのことを大切だと、 必要だと思い、そして私たちにそのことを教えられているんじゃないでしょうか。
放送は第47回・2015年の番組の再放送です。
しみも咎も汚れもなき
小羊わが主は屠られしや
こはわがため十字の上に
釘もて裂かれし御身体なり
こはわがため呪い受けて
流させ給いし君が血なり
こはわがため与え給う
命の糧なり飲み物なり
#41
ルターは、「イエスが死なれたのは、つい昨日のことのように感じる。」 そんなことを言っているそうなんですね。 そうなんですよね、イエスの死、これは日々問われていることだし、 体験していかなきゃいけないことだなって思うんです。
僕が最初に聖餐式に与った時、「しみもとがも」という曲が賛美されて、 ずっしり重いものを感じたんですね。 上手く言えないんですけど、イエス様の流した血、裂かれた体、 そこまで降りていって、そこを通らなきゃいけない。 その体験をするために聖餐があるんだって思ったんです。
もう何年も前のことですけど、今思うんです。 あの時に感じた重さ、それはイエス様が負った 途方もない僕らの罪の重さなのかもしれない。この重さを感じなきゃいけない。 それは、どれだけの愛なんだということだと思うんです。 これは体験することでしか私たちはそれを得られないんじゃないかなと思います。
放送は第46回・2015年の番組の再放送です。
あなたとともに、きょうもあゆませてください
あなたとともに、きょうもあゆませてください。
あなたをよろこび、あなたと語り、
あなたの胸に抱かれて、
あなたとともに、きょうもあゆませてください。
あなたと笑い、あなたと泣いて、
あなたの胸で眠りたい。
あなたとともに、きょうもあゆませてください。
#40
これは僕が書いた曲で、
「あなたとともに、きょうもあゆませてください」という言葉が繰り返されているんです。
でも、思ったんですね。その歩む、きょうの私の道が、ものすごく苦しい道だったら…。 イエス様の歩みはどうだったでしょうか。
新約聖書のヘブル書5章にこういう言葉があります。
キリストは御子であられるのに、お受けになった多くの苦しみによって従順を学び
弟子たちにも捨てられる苦しみを受け、
「私は悲しみのあまり死ぬほどです」と言ったイエス様。
その苦しみを通らなかったら、十字架はなかった。
僕も今までの人生で、本当につらかったことがありました。
その時に、しかし神様が一番僕に近づいてくださって…。
己の十字架を背負って、イエス様についていくというのは
そういうことなんじゃないかなと思います。
放送は第45回・2015年の番組の再放送です。
There is a balm in Gilead
to make the wounded whole,
there is a balm in Gilead
to heal the sin-sick soul.
Sometimes I feel discouraged
and think my work’s in vain,
but then the Holy Spirit
revives my soul again.
#39
黒人奴隷たちは、社会的にはもう人間と思われていなかった人たちです。
彼らは体もボロボロになって、心なんかもうなくなっているんじゃないかって、
自分たちでもそう思うことは日々あったんじゃないでしょうか。
もう自由がゼロ以下だった。
だから、彼らは求めた。正しさではなく、その弱さに、
イエス様は触れてくださるために来たんだと。
今日お届けする「ギルアデの乳香」という曲は、
まさにそれを確信して歌っているんじゃないかなと思うんですね。
放送は第44回・2015年の番組の再放送です。
Your only Son, no sin to hide,
But you have sent Him from Your side
To walk upon this guilty sod
And to become the Lamb of God
Oh Lamb of God, sweet Lamb of God,
I love the holy Lamb of God.
O wash me in His precious blood.
My Jesus Christ, the Lamb of God.
#38
今日は旧約聖書のイザヤ書53章を読んでみたいと思います。 彼はさげすまれ、人々からのけ者にされ、 悲しみの人で病を知っていた。 人が顔をそむけるほどさげすまれ、 私たちも彼を尊ばなかった。 誤解されたり非難されたりするときに、言い返したいなって思うときに、 このイザヤ書のイエス様が目の前に昇ってきます。 彼は痛めつけられた。 彼は苦しんだが、口を開かない。 ほふり場に引かれていく羊のように、 毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、 彼は口を開かない。 このイエス様を思い浮かべるときに繋がってくるのが、 今日ご紹介する「Lamb of God」っていう曲です。
放送は第43回・2015年の番組の再放送です。
Why should I feel discouraged, why should the shadows come
Why should my heart be lonely, and long for heaven and home
When Jesus is my portion? My constant Friend is He
His eye is on the sparrow, and I know He watches me
His eye is on the sparrow, and I know He watches me
I sing because I’m happy, I sing because I’m free
His eye is on the sparrow, and I know He watches me
Oh I feel I’m right, just I sing, Oh I feel I”m right, just I sing yes!
And I know He watches over me
#37
これは聖書のイエスの言葉にインスパイアされて作られた歌です。
人にどう思われるかを気にして、空気を読んで、恐れていた弟子たちに、
イエスが語りかけた言葉なんです。
僕たちもこれを恐れていると思うんですよね。
そんな僕らに、これはイエス様が励ましてくださった言葉、そういう歌なんですね。
全部、全部わかっているよ。
そして宣言するんです。
I know He watches me
放送は第42回・2015年の番組の再放送です。
O come, all ye faithful, joyful and triumphant,
O come ye, O come ye to Bethlehem!
Come, and behold Him, born the King of angels!
O come, let us adore Him;
O come, let us adore Him;
O come, let us adore Him, Christ, the Lord!
#36
今日は僕の大好きな「O Come, All Ye Faithful」を紹介したいと思います。
強烈なゴスペルなんですね。Come、Come、Come、来なさいと。
僕、イスラエルに行った時に、ベツレヘムの聖降誕教会、地下の薄暗い石の部屋の洞窟で、
そこがヨセフとマリアが泊まっていた馬小屋と言われているところなんですけど、
そこで、誰が歌うともなく「O Come, All Ye Faithful」をみんなで歌い始めて、
イエス様のご降誕に思いを馳せたんです。
でもですね、この曲を歌う時に、そのベツレヘムの洞窟というよりも、
毎日僕らは、イエス様が罪をあがなってくださったっていうところに戻って行きたい。
僕たちの魂は、そこにComeしたいんですね。
そこが僕らのベツレヘムなんじゃないでしょうか。
ゴスペルっていうのは本当に強くそのことを
自分たちの胸に刻むために歌う歌でもあるなって、いつも思うんですね。
放送は第41回・2015年の番組の再放送です。
Deep river, my home is over Jordan,
Deep river, Lord, I want to cross over into campground.
Oh, don’t you want to go to that gospel feast
That promised land where all is peace?
#35
私達は黒人奴隷の時代に生まれたわけではないけれども、
様々な鎖に繋がれていると思うんですね。
僕は福島県で生まれたんで、3月11日、東日本大震災が起きた後、
すごく心を痛めて祈ってたんですけど、
「深い川を越えて さあ行こうよ 懐かしい心のふるさとさして」
っていう歌詞が頭の中で回り始めて…。
深い川―まるで超えられないように目の前に立ちはだかる現実
越えていこうよ 懐かしい心のふるさととして
心のふるさと―私達が本当に休むことができる、主がそこにおられる場所
これは本当に心揺さぶられる曲だと思うんですね。
なぜなら私達一人ひとりにとってのディープリバーが必ずあるからです。
放送は第40回・2015年の番組の再放送です。
#34
今回は最も知られている黒人霊歌の一つ「Deep river」をご紹介します。
アメリカで奴隷制に反対したクエーカー教徒たちは、
ノースカロライナ州を拠点に、奴隷たちをカナダに逃がす活動をしていました。
そこにディープリバーと言われる川があったんです。
実際は小さな川だったようですが、黒人奴隷たちにとってこの川を越えるというのは、
あらゆる危険を乗り越えて、自由になることを意味していました。
彼らは自分たちの本当に帰りたかった故郷を思って歌ったとも言われています。
ディープリバーは、まさしく彼らにとっては、
そこに行けば逃がれることができるかもしれないという、希望の光でもあり、
そこにある障害、困難でもありました。
あなたにとっての深い川は何でしょうか。
放送は第39回・2014年の番組の再放送です。
Oh, happy day (Oh, happy day)
Oh, happy day (Oh, happy day)
When Jesus washed (When Jesus washed)
Oh, when He washed (When Jesus washed)
When Jesus washed (When Jesus washed)
He washed my sins away (Oh, happy day)
Oh, happy day (Oh, happy day)
#33
前回もご紹介した「Oh happy day」
「THAT FIXED MY CHOICE」という賛美歌の歌詞をそのまま使っているんです。
これはブラックゴスペルではよくあるパターンで、昔からの賛美歌を、
今の人たちが好きなスタイルにアレンジしたり、メロディーを変えてしまうこともあります。
そうやって時代、人種、国境を越えて受け継がれていく。
ゴスペルは、それを恐れなくやっていく文化があるなと思うんですね。
この「Oh happy day」はその一つのターニングポイントにもなった、
革命的な歌だと思うんです。初めはすごく批判されて、保守的な教会から叩かれたそうです。
でも、ヒッピーやリベラルな人たちが教会に集まるようになっていった。
ましてやこの日本にまでですね、ゴスペルブームが教会の外で起こって、
そして「Oh happy day」と、自分のストーリーとして歌うようになる人たちがいるんですね。
放送は第35回・2014年の番組の再放送です。
#32
今日は皆さんがよくご存知のきっと世界で一番有名な
コンテンポラリーゴスペルだと思うんですけれども
「Oh Happy Day」をご紹介します。
1994年に日本でも公開された「天使にラブソングを2」に入っている曲で、
今、僕がこの番組で喋っているのも、
きっとこの映画があって日本でゴスペルブームが起こったからじゃないかなと思うんです。
この歌の力は、一言で言えば、全てのボーダーラインを超えた曲なんですね。
まずアメリカにおいても、普通の宗教歌は超えられなかった
ビルボードのヒットチャートでドーンと上がっていった最初の曲だったんですね。
今でもゴスペルをやる人がまず初めに覚える曲で、
実際に自分が「Oh happy day」って歌ってみると、本当に解放される、
ゴスペルの魅力が詰まっている曲です。
放送は第34回・2014年の番組の再放送です。
聖なる主の前に 頭をたれ
心しずめよ 主がおられる
聖なる主の 聖所に立ち
心を静めよ 主がおられる
#31
今日ご紹介するのは「聖なる主の前に」という曲です。
広く世界で歌われているんですけど、実は僕は知らなくて、
教会福音賛美歌のレコーディングを通して知ることができて、
本当に豊かな賛美の世界が広がって感謝しているんです。
僕がこの曲いいなと思ったのは、
神の前で頭をたれて、心しずめる、そこに導いてくれるところです。
これって本当に大切なことだなと思います。ただ黙って、自分の考えを全部置いて…。
アレンジも、この曲からインスパイアされて、
ハワイアンというか、癒されるような、
自然の音を喚起するような楽器でのアレンジにしてみました。
ぜひ聴いてみてください。
放送は第33回・2014年の番組の再放送です。
心熱くして耳を傾け
ほめたたえるのは主イェスの御名
主を愛する熱い思いは主が私を愛されたから
#30
黒人教会で本当に愛されている賛美歌を今日は紹介したいと思います。
「Oh How I Love Jesus」という曲で、「心熱くして」というタイトルで
日本語になっています。歌っていると引き上げられていくような曲だなと思います。
19世紀のアメリカのトラディショナルなメロディで、
誰が作ったかはもう分からないんですが、
歌詞はフレデリック・フィットフィールドというイギリス人によって書かれました。
英語の原詞は韻が踏まれた短い歌詞で、すごく入ってきやすいんです。
それを日本語に訳すっていうのは、非常に困難があったと思うんですけど、
引き上げられるようなところにフォーカスされていて、
本当に心熱くなる賛美になっていると思います。
放送は第32回・2014年の番組の再放送です。
Oh, I know that I can make it
I know that I can stand
No matter what may come my way
My life is in Your hands
With Jesus I can take it
With Him I know I can stand
No matter what may come my way
My life is in Your hands
#29
ゴスペルって、理屈からじゃなくて、体験から入るんですね。
頭で理解するものではない、それを飛び越えていく。そういう激しさがあると思うんです。
実は韓国ではあんまりブラックゴスペルは人気が出ないんです。
韓国の方って激しいんですよね。激しく自分の感情を発露する、叫ぶカルチャー。
だから、敢えて同じ叫ぶブラックゴスペルはいらないのかもしれません。
でも日本人って、叫べないで内に込めて、本当に我慢し我慢して頑張っていくような…。
そう僕らにとって、このゴスペルっていうのは
本当に神様からの贈り物だったんじゃないかなって思います。
放送は第31回・2014年の番組の再放送です。
I need you, you need me
We’re all a part of God’s body
Stand with me, agree with me
We’re all a part of God’s body
It is his will, that every need be supplied
You are important to me, I need you to survive
You are important to me, I need you to survive
#28
「あなたを必要としている」「愛している」
日本人はそういうことをなかなか口に出して言わない民族だと思います。
でもゴスペルを歌うことによって、それをあからさまに言える、感じられる。
そうすると歌いながら何か解放されていくように思います。
そして、ゴスペルの歌詞は英語なんですよね。
もし日本語だったら、これほど多く日本人でゴスペルをう人たちは増えなかったと思うんですね。いきなり日本語で「神があなたを愛しています」と歌わされると、
その歌詞にブロックされるというか、入っていくものも入っていかないと思うんです。
でも英語だったことによって、自然に、
「息のある者よ皆、主をほめたたえよ、ハレルヤ」って、
クリスチャンじゃない人も、みんなが歌っている、そういうことが起こってるんですね。
放送は第30回・2014年の番組の再放送です。
#27
映画「天使にラブソングを」がきっかけで日本でブームが起きたゴスペルですけど、
日本では本当に独特な進化を遂げてきたなと思ってるんです。
一番特殊なのは、歌っている人のほとんどがクリスチャンじゃないということ。
これは世界的にも珍しいことです。なぜ日本人がゴスペルに心惹かれていったのか…。
今日ご紹介する「I Need You To Survive」は、
日本人がゴスペルに惹かれた一つの大きな側面を描き出している歌だなと思うんですね。
「I need you, you need me.We're all a part of God's body」
と繰り返していく歌なんですけども。
必要だ。愛されてる。
私たちの社会は、こういうことがなかなか感じられない社会じゃないかなと思うんです。
でもそれが、ゴスペルを歌う中ですごく感じられて、
聞いて感動して、歌って感動して、自然に涙が出てきたりする。
それを本当に僕も今まで実感してきました。
放送は第29回・2014年の番組の再放送です。
#26
今日ご紹介したいのは「This Little Light of Mine」という黒人霊歌です。
「私の中にあるこの小さな光を今日、輝かせます」という歌詞です。
輝かせるかなとか、輝かせてくださいじゃなく、「輝かせます」宣言していくんですね。
1960年代のミシシッピー、黒人たちが市民権を得ようとした公民権運動のリーダーで、
ファニル・ハーマーさんという方がいました。
彼は1964年、民主党の全米大会で、黒人の私たちも民主党の代表として選んでください、
という運動をしたんですけど、白人によって却下されてしまったんです。
その時にこの「This Little Light of Mine」を歌った
というエピソードが残っているんですね。
私たちにとっても、日頃の生活の中で、またこの社会の中でも、
本当ゴスペルっていうのはただのエンターテイメントじゃないんですね。
あらゆる局面で私たちに力を与えてくれる神の力なんじゃないか、
そして宣言していく力なんじゃないかなというふうに思います。
放送は第28回・2014年の番組の再放送です。
イェスよ、愛の御手をのべて
助けたまえ、われを
嵐ふいて嘆くときも
立たせたまえイェスよ
#25
今回は、ゴスペルの父と言われる作曲家トーマス・A・ドーシーの、
悲しみから生まれた名曲、その背後にあるドラマを紹介ます。
聖歌557番「慕いまつる主なるイエスよ」として世界中で愛されている曲でもあります。
彼はもともとブルースのシンガーだったんですけど、
クリスチャンになってゴスペルを歌うようになった人です。
ある時、臨月だった妻を残して、隣町の伝道集会に出かけるんですけど、
彼が留守の間に、その奥さんが出産し、その後亡くなってしまい、
生まれた赤ちゃんもすぐに亡くなってしまうんですね。
その後にできたのがこの曲です。
彼は、もう曲を書くことも歌うことも辞めようかと思ったそうです。
でも、この悲しみの中から、心の奥底から絞り出すように出てきた、
そうしてこの曲が生まれてきたと語っています。
放送は第27回・2014年の番組の再放送です。
What a friend we have in Jesus,
all our sins and griefs to bear!
What a privilege to carry
everything to God in prayer!
#24
今日は「What a Friend We Have in Jesus」
日本語では「慈しみ深き」という賛美歌をシェアしたいと思います。
僕が最初に教会に行き始めた時に覚えた賛美歌の一つです。
この歌詞を書いたジョセフ・スクリーヴンさんは、
人生で二度も婚約者を亡くすという悲劇を経験した。
その彼が、故郷で病気のお母さんのために送った詩がこの「慈しみ深き」なんですね。
二番の歌詞にも彼の心が現れてると思います。
Have we trials and temptations?
Is there trouble anywhere?
彼の人生はもう本当にトライアルズ&トラブルなんですね。
その彼がこう歌う。
Jesus knows our every weakness.
僕が初めてこれを歌った時、作者のことは知らなかったんですけど、
すごい熱い何かを感じたんです。
Jesus knows
これが彼の悲しみの中からの叫びだったんだなって、今はリアルに思います。
放送は第26回・2014年の番組の再放送です。
Nobody knows the trouble I’ve seen
Nobody knows the trouble I’ve seen
Nobody knows but Jesus
Glory hallelujah!
Sometimes I’m up, sometimes I’m down
Oh, yes, my Lord
Sometimes I’m almost to the ground
Oh, yes, my Lord
#23
今日はリスナーの方からいただいたメールをご紹介します。
ゴスペルといえば、映画「天使にラブソング」をのイメージしかなかった私が、
番組を聞きながら、ゴスペルが持つ物語の中に身を置くような経験をしています。
今年、父を天に送りました。番組で、奴隷の父親が雇い主に鞭打たれた後、
一人泣いている姿をその奴隷の子供が見ているという場面が語られたとき、
私もその子と一緒にその場にいました。父親の背中を見ていました。
父の悲しみ、苦しみのすべてを到底知ることはできない、
ただその背中を見つめるばかり。
But Jesus
この短い言葉が、ああそうだ…と。
ゴスペルの物語の中に私自身の物語を持ち込んで経験することで、
心の固い殻にひびが入るように感じます。
これからもゴスペルが持っている物語の世界に導いてください。
楽しみにしています。
放送は第25回・2014年の番組の再放送です。
Steal away, steal away
Steal away to Jesus
Steal away, steal away home
I ain’t got long to stay here
My Lord, He calls me.
He calls me by the thunder.
The trumpet sounds within my soul.
I ain’t got long to stay here.
#22
白人たちは、奴隷たちによる反乱が起きることを非常に恐れていました。
だから黒人たちの秘密の集会にも非常に警戒し、見つけると処罰した。
背中の骨が剥き出しになるくらい鞭打ち、
他に誰がそこにいて何をしていたか問い詰めたという記録も残っています。
ジョージという牧師でもあった奴隷は、
500回鞭打ちをされて、後に逃亡するんですけど、
捕らえられて、最後は役人によって生きたまま焼かれたと言われています。
それでも彼は賛美をした。
そのことを思うと今もゴスペルがこんなにも私たちの心に、
強く訴えかけてくることに納得できる。
彼らが命がけで賛美した歌だから、
何も考えないでただゴスペルに触れただけの私たち日本人をも、
感動し涙させる力があるんだと思います。
放送は第24回・2014年の番組の再放送です。
#21
この「Steal away」という曲、命がけの賛美なんです。
奴隷たちは、自分たちが働かされている畑から遠く離れた森の奥に小屋を用意して、
そこで秘密の集会を開いて、夜遅く、地面に身を投げ出して、祈りの歌を捧げた。
白人の奴隷主たちに気づかれないように、
steal away to Jesus
こっそりひそやかに祈りの小屋に向かって逃げていく。
そうやって逃げていった祈りの小屋で、一人一人がジーザスに逃げていった。
歌いながら、祈りながら。そういう時間だったと思うんですね。
彼らはどんなに命がけでその時間を持とうとしていたか…。
放送は第23回・2014年の番組の再放送です。
My Lord, what a morning.
My Lord, what a morning,
My Lord, what a morning,
When the stars begin to fall.
You’ll hear the trumpet sound,
To wake the nations underground,
Looking to my God’s right hand,
When the stars begin to fall.
#20
この「My Lord What A Morning」の「モーニング」、
実はほとんど発音が同じで別の意味の言葉とのダブルミーニング、
あるいはトリプルミーニングだとも言われているんです。
一つは「mourning―悲しみ」、もう一つは「moaning―うめき声」。
奴隷たちは日の出とともに働き始める。
「When the stars begin to fall」という歌詞は、
星が一つ二つ消えていく、その夜明けのことを歌っていると思う。
「主よ、何と悲しいことでしょうか」
苦しい労働の長い一日の始まりに、この歌を口ずさんだ。
ニグロスピリチュアルの研究をされている北村崇郎先生はこう書かれています。
「美しい歌の陰に何と悲しい人生があったことか。
…皮膚の色が黒いという理由だけで奴隷にされ、
この人生を強要されていたとはまさに驚きではないか。
魂を揺り動かす感動を与えてくれるスピリチュアルの数々の影に
我々の想像を絶する悲惨な人生があったことを心に刻もうではありませんか。」
放送は第22回・2014年の番組の再放送です。
#19
黒人霊歌には、世の終わりの時をビビットに描いた歌があります。
そこには、あまりにも苦しい奴隷として生きる日々の中で、
将来のビジョンを描いて、そこに憧れ、希望を持って、今を生きていく、
そういう彼らの思いが溢れてるんですね。
聖書には、この終わりの日のことが書いてあります。
黒人奴隷たちはその言葉を思いながら、互いに慰め合った。
きっとこの日を彼らほど待ち望んでいた人たちはいないんじゃないかと思う。
僕たちも、本当にこの世を去りたいと思うほど、
この地上での日々がやりきれない時がある。
その時に、黒人たちがどれほど慰められたか分からない、
天への希望が溢れる言葉によにって、僕らも待ち望みたいなって思います。
放送は第21回・2014年の番組の再放送です。
#18
僕の家にキング牧師のポスターがあるんですけど、
そこに彼のこんな言葉が書いてあるんです。
True peace is not merely the absence of tension.
It is the presence of justice.
正義が存在しなければ、単に争いがないからって、真の平和はではない。
彼はそう言ったんですね。
僕らの職場、社会、家庭、暮らしている場でも、争いがないけど、
そこには正義がないということがあると思うんです。
当時のアメリカの白人たちと同じように、
自分を守りたい一心で、正義が後回しになってしまう。
キング牧師のこの言葉は、そのことを僕らに思い出させてくれる。
事勿れ主義じゃいけないと。
そしてそれは、イエスが本当に僕たちに教えてくれたことなんじゃないかなと思っています。
放送は第20回・2014年の番組の再放送です。
#17
今日はリスナーの方からいただいたメールをご紹介します。
いつも楽しみに聞いています。
さて、 I Have a Dreamの感動的なキング牧師の演説の中でこのような一節がありました。
「私には夢がある…黒人も白人もユダヤ教徒も異教徒も
プロテスタントもカトリックも全ての神の子たちが手を取り合って、
あの古い黒人霊歌を口ずさむ…。
『Free at last Thank God Almighty I'm free at last』
(ついに自由だ、全能の神に感謝せん、ついに自由になった)」
この古い黒人霊歌とは何の曲か分かりますか?
これは「Free at last」っていう黒人奴隷の叫びから来てる霊歌なんです。
彼らはフリーじゃなかった。家族とバラバラにされ、鞭打たれ、いつも自由がない。
その彼らが「私はついに自由になった」そう歌った。
これは彼らが死を迎える時のイメージだと思うんですけど、それだけじゃない。
イエスを信じた。その時のことでもあると僕は思います。
放送は第19回・2014年の番組の再放送です。
You may haven this word
Give me Jesus
I heard my mother said
I heard my mother said
Give me Jesus
Give me Jesus
You may haven this word
Give me Jesus
#16
黒人霊歌を若い世代に受け継ぐ活動をしていた
ルーヴェニア・ポインターさんという方はこう語っています。
「黒人奴隷は、人も物も権力も、この世に何も頼るものがなかった。
だから、本当に『Give me Jesus』とだけ言えたのではないか。」
私たちは色々なものが溢れ過ぎた世の中にいるから、
「Give me Jesus」とシンプルに言えないのかもしれません。
ポインターさんはこうも言っています。
「私たちは今、奴隷制度の中には生きていないけれども、
物質主義に縛られているんじゃないか。」
物質主義の奴隷。でも、そこでこそ、
まさしく奴隷制度の中で天を見上げて歌った歌―ゴスペルを歌っていきたい。
そこで私たちも「Give me Jesus」そう叫ぶ者でありたいなと思います。
放送は第18回・2014年の番組の再放送です。
#15
今日は僕も大好きな一曲「Give me Jesus」を紹介します。
本当にシンプルな叫びの歌です。
もう本当になんて言うんでしょう、一行、一行、一行っていうだけの歌詞で続いていく、
黒人奴隷の痛み、孤独、苦しみ、そこから生まれた曲なんですね。
彼らは自分の子供や家族、友人とも引き離されて売られていく。
人間的なものが全部奪われた状況で、誰も助けてくれない。
まさしくその悲しみに満ちた怒りが、奴隷生活の中には満ち溢れてるんですね。
でも、この曲は怒りの歌じゃないんです。
だからこそ、その彼らが「Give me Jesus」って言えた。
この真っ暗闇の中で、ただ「イエス様をください」と。
放送は第17回・2014年の番組の再放送です。
There is a balm in Gilead
to make the wounded whole,
there is a balm in Gilead
to heal the sin-sick soul.
#14
黒人奴隷だちはどれほど毎日落ち込んだか。働いても働いても報いはない。
「神様、何のために私は働いているんでしょうか。」
私たちだってそう思うときありますよね。全然成果が得られなくて、虚しくなる。
その時、その弱った心にこそ、神様のHoly Spiritが私たちの魂に触れてくださって、
Balm in Gilead(ギルアデの乳香)のように、魂に塗られて、
もう一歩そこから歩いていくことができる。
私たちはどうしていいか分かんないし、また落ち込んでしまう。
だけど、「ジーザスに頼ればいい」と。
黒人霊歌っていうのは、子供でもわかる言葉でシンプルに伝えてくれる。
だから僕は好きなんですね。
難しい言葉はいらない。本当に大事なことだけ叫ぶ。
それが黒人霊歌なんじゃないかなというふうに思います。
放送は第16回・2014年の番組の再放送です。
#13
今日ご紹介するのは疑問文を肯定文に変える歌です。
旧約聖書エレミヤ書8章に、預言者エレミヤがイスラエル人の艱難を預言し、
「ギルアデには人を癒す妙薬はないのか?」と問いかける場面があります。
黒人奴隷たちは日々の苦しみをこのイスラエル人の苦しみに重ねる。
ところが彼らはエレミアの問う疑問文を、肯定文に変えてしまったんです。
ギルアデには乳香がある!傷ついた私たちを、
この罪でいっぱいの私たちの魂を癒す妙薬がある!
鞭打たれ、生きる意味を考える毎日の中で、彼らは歌った。
Jesus is balm in Gilead.
彼らのこのシンプルな信仰の歌「Balm in Gilead」。
すごくメロディもきれいな曲です。
今日はこれを日本語に訳した賛美歌「ギルアデの乳香」聴いていただきたいと思います。
放送は第15回・2014年の番組の再放送です。
Oh Lord, I just come from the fountain.
I’m just from the fountain, Lord.
Just come from the fountain.
His name so sweet.
Poor sinner, do you love Jesus?
Yes, yes, I do love my Jesus.
Sinner, do you love Jesus?
His name so sweet.
#12
前回もご紹介した「His Name So Sweet」という黒人霊歌では、
「I just come from the fountain.」という歌詞が繰り返されます。
fountain―泉っていいですよね。
ゴスペルの中で尽きることのない、溢れてくるものを表現する、この「Fountain」。
彼らの中ですごい助けというか・・・嬉しかったんじゃないかなって思います。
それに続く歌詞はこうです。
Poor sinner, do you love Jesus?
Yes, yes, I do love my Jesus.
これはコール・アンド・レスポンスというスタイルで、
リーダーが「Poor sinner, do you love Jesus?」って歌うと、
他の奴隷たちが「Yes, yes, I do love my Jesus.」って応え合う。
ずっと今も踏襲されてきている、黒人の信仰の特徴だと思うんです。
「お前はイエスを愛しているか?」と、彼らは身振り手振り、
また踊りやスキットで、本当に表現力豊かに歌うんです。
信仰から逸れていかないように、また逸れていっている人を戻すように。
放送は第14回・2014年の番組の再放送です。
#11
今日ご紹介する黒人霊歌「His name so sweet」。
僕は最初この「sweet」っていう単語のニュアンスがわかんなかったんですね。
でもイエス様と出会って、リアルに「 His name so sweet」を実感しているところなんです。
新約聖書ヨハネ福音書4章に出てくるサマリアの女は、
ユダヤ人の間で迫害されていて、公的な場所にも出ていけず、
暑い砂漠の昼に水を汲みに出て行った。そこでイエスが彼女に語りかけ、
二人のやり取りが続くんですね。
そこでイエスは言うんです。
「私が与える水はその人のうちで泉(fountain)となり、永遠の命への水が湧き出ます。」
黒人奴隷にとっては、もう僕には語り尽くせないぐらい、
このサマリアの女の心と自分の境遇がピタッと重ね合わせられたんじゃないかなと思う。
そういう苦しいところを通ったからこそ「His name so sweet」
この「sweet」の意味が本当にわかるんじゃないかなと思うんですね。
放送は第13回・2014年の番組の再放送です。
暗い夜が来て何も見えない
かすかに聞こえる hold on
涙も枯れて途方に暮れた
言葉にならない hold on
hold on
hold on
Keep your hand on the plow hold on
苦しみの向こう祝福があるって
信じ続けよう hold on
右も左も閉ざされたなら
天を見上げよう Just hold on
hold on
hold on
Keep your hand on the plow hold on
#10
白人たちから鞭打たれながら、畑を耕していかなきゃいけない。
これが黒人奴隷たちの日常生活だったと思います。
私たちの日常にも、本当に辛いいろんなことに打たれている時があると思います。
先週も聞いていただいた「Hold on」という歌、
私が日本語の歌詞を黒人霊歌に付け加えているんですけど、
この歌詞は、あの東日本大震災の後に生まれてきたんです。
暗い夜が来て何にも見えない。
かすかに聞こえるHold on。
涙も枯れて途方に暮れた。
言葉にならないHold on。
苦しみの向こう祝福があるって。
信じ続けようHold on。
右も左も閉ざされたなら
天を見上げようJust hold on。
奴隷制度という強制的に置かれた環境、この究極の弱さの中から生まれてきた歌、ゴスベル。
これが私たちにどうあるべきかを見せてくれてるんじゃないかなというふうに思います。
放送は第12回・2014年の番組の再放送です。
Deep river, my home is over Jordan,
Deep river, Lord, I want to cross over into campground.
Oh, don’t you want to go to that gospel feast
That promised land where all is peace?
#9
奴隷制度はゴスペルを語るときに絶対に外せない、一番源の部分です。前回お話した映画「それでも夜は明ける」でも、本当にその生々しい厳しさ、辛さが描かれていましたけど、このゴスペルの出発は奴隷制度なんですね。
この試練、困難、厳しさ、ここを体験する、ここを実際に生き抜いていくというところからしか、ゴスペルは生まれてこなかったと思っています。
そしてまた彼らにとって、励まし、慰めや希望を確信させるゴスペルがあったから生き抜いてこれて、そしてまた歌が生まれてきたと思うんですね。
放送は第11回・2014年の番組の再放送です。
#8
「12 years a slave」(邦題「それでも夜は明ける」)という実話を元にした映画があります。主人公はアメリカ北部に生まれ育った、奴隷ではない自由黒人。ところが拉致されて南部に連れていかれ、奴隷として働かされる。そして12年経って、自分が自由黒人だと証明でき、家族の許に帰るという壮絶な話なんです。
その映画にも出てくるんですけど、当時クリスチャンが奴隷制を支持してました。聖書の言葉を使って奴隷制を正当化する、そういう現実がありました。
今の僕らが彼らを批判するのはすごくイージーなことだと思います。でもその映画を見て僕は、自分の内側にある弱さと罪をすごく感じました。たとえ今、奴隷制がなくても、人を支配したり、この方が楽だ、効率的だ、そのために人を犠牲にする。そういう同じ罪の種、本当に僕らの中に大きくあるなと…。
そういう人間の罪の中で、この主人公は、家族と会いたい―これは愛の力だと思いますけれども、希望を持ちます。この愛の力しか、罪を克服することはできないんじゃないか…。イエス様はその愛の動機によって来てくださったんだ、そう思ったんです。
放送は第10回・2014年の番組の再放送です。
Wade in the water
Wade in the water
Wade in the water, children
Wade in the water
God’s gonna trouble the water
See that host all dressed in white,
God’s a gonna trouble the water.
The leader looks like the Israelite,
God’s a gonna trouble the water.
#7
今日は「地下鉄道(underground rail road)」のことをお話したいと思います。これは黒人奴隷たちのアメリカ北部州やカナダへの逃亡を援助する秘密組織でした。この活動の中でも黒人霊歌は大きな役割を果たしたと言われています。
奴隷の苦しみ、それは僕らはもう想像するしかない、また想像しがたい…。その日常の苦難の中で、彼らが歌い、何を思って、そして神に希望を見出していったか。口で言うのは簡単なんですけども、この生活から逃れたい、解放されたい、すごくこう何とも言えないリアルな苦しみの中で生きていた彼らの複雑な思いというのがあったと思うんですね。
そういう中でこの「地下鉄道」は、食べ物や着る物を援助したり、北へ行く道を教えたり、さらには馬車やボートに乗せて次の場所まで護送もしたと言われています。まさに命がけで。
彼らは、奴隷主たちが追跡のために放った犬から逃亡奴隷たちを逃れさせるために川を渡らせた。その歩いて川の中に入っていくことを歌った「Wade in the Water」という歌を今日は聞いていただきます。
2014年の番組の再放送です。
Steal Away
Steal Away
Steal Away to Jesus
Steal Away
Steal Away home
I ain’t got long to stay here
#6
黒人奴隷たちは魂の解放と自由の希望を歌に託しました。そして実際の自由を得るために、歌は彼らの大切な武器になったと言われています。
例えば「Steal Away」という曲。これを誰かがハミングで歌い始めると、それを聞いた人がまた歌う、そうして遠く離れた畑までバトンを渡すように歌い継いでいく。これは、奴隷主に気づかれないように、夜中にハッシュハーバーで集まるぞと知らせるサインだったと伝えられています。
奴隷たちの中には北部に逃亡した人もいました。奴隷主たちは逃亡奴隷を追うのに犬を使うんですけど、犬は鼻が一回水に入ると効かなくなるんですね。だから奴隷たちは川に入った。まるで紅海を渡るイスラエルの民のように。その時に「Go Down Moses」という黒人霊歌を歌って、今晩川を渡って逃げるぞと、逃亡をヘルプしてくれる人たちに伝えたとも言われています。
僕は黒人霊歌がこういう現実の自由への歌だったと知って、だからこそ今、僕ら日本人にも、その強さ、濃さ、希求力が伝わるんじゃないかって思ったんです。
2014年の番組の再放送です。
Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
A long, long way from my home
A long, long way from my home
Sometimes I feel like I’m almost gone
Sometimes I feel like I’m almost gone
Sometimes I feel like I’m almost gone
We are up in the heavenly,
heavenly land
We are up in the heavenly of land,
true believer, a long way from home,
a long way from my home.
#5
今回からしばらくゴスペルの歴史に触れながら掘り下げていきたいと思います。
黒人霊歌は1730年代にそのルーツを持ち、18世紀半ばから後半にかけて歌われた黒人奴隷たちの歌と言われています。
彼らは1日の苦役を終えた後、仲間と秘密の場所で集まり、祈り、歌い、踊った。それは写真にも残っていないし、今となっては正確には把握できないのですが、「ハッシュハーバー」と呼ばれる奴隷たちの場所です。
見つかってはいけない、隠された教会。奴隷主に発見されれば刑罰が加えられる。それでも彼らは集まりました。
苦難の中で、隠された場所で、長い時間かけて、黒人霊歌は形作られていったんですね。
歌い、祈り、神に助けを求めて叫び、踊った。時には一晩中。
2014年の番組の再放送です。
Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
A long, long way from my home
A long, long way from my home
Sometimes I feel like I’m almost gone
Sometimes I feel like I’m almost gone
Sometimes I feel like I’m almost gone
We are up in the heavenly,
heavenly land
We are up in the heavenly of land,
true believer, a long way from home,
a long way from my home.
#5
今回からしばらくゴスペルの歴史に触れながら掘り下げていきたいと思います。
黒人霊歌は1730年代にそのルーツを持ち、18世紀半ばから後半にかけて歌われた黒人奴隷たちの歌と言われています。
彼らは1日の苦役を終えた後、仲間と秘密の場所で集まり、祈り、歌い、踊った。それは写真にも残っていないし、今となっては正確には把握できないのですが、「ハッシュハーバー」と呼ばれる奴隷たちの場所です。
見つかってはいけない、隠された教会。奴隷主に発見されれば刑罰が加えられる。それでも彼らは集まりました。
苦難の中で、隠された場所で、長い時間かけて、黒人霊歌は形作られていったんですね。
歌い、祈り、神に助けを求めて叫び、踊った。時には一晩中。
2014年の番組の再放送です。
Oh, Plenty Good Room
Plenty Good Room
Good room in my father’s kingdom
Plenty Good Room
Plenty Good Room
Why don’t you choose your seat and sit down?
I would not be a sinner
I’d tell you the reason why
Cause if my lord should call on me
I wouldn’t be ready to die
#4
これは名もない黒人奴隷が作ったゴスペルで、曲調はブルースと何ら変わらないんですね。
どうしようもないブルーな感情の爆発、その自分に焦点が当たっている歌がブルース。そしてゴスペルも感情の叫びがあります。じゃあ何が違うのか。
ゴスペルのゴスペルたる所以は、その感情の叫び自体じゃないんですね。そこに留まるんじゃなくて、天を仰ぐ。その目線にこそゴスペルのエッセンスが隠されていると思うんです。
ブルースは、「俺もそうだ」「私も辛い」、その共感による横のつながりの歌だと思うんですね。
ゴスペルは、その自分というものはもう手放しちゃう。そして神に、心も体も全部委ねて歌う。自分が無くなるんじゃなくて、神様に引き上げられていくような…。
僕はイエス様に出会って、僕の歌が本当にゴスペルになった時に初めて、ブルースとゴスペルの違いが分かったような気がします。それは知識じゃないし、どっちが好きかということでもなくて、本当に体験したんだと思います。
2014年の番組の再放送です。
#3
僕は高校生の頃にブルースを聞いて、おじいちゃんがうなりながら歌ってたんですけど、当時ハードロックでギターを歪ませて叫んでた僕よりも、遥かに感情の爆発を感じたんですよね。
お金がないとか女房に逃げられたとか仕事がないとか、リアルな日常を歌うブルース。その節回しの全てに、どうして人生は、俺はこうなんだっていう叫びを感じて、共感しました。自分のことを自虐的に歌うことで少し楽になるような…。
ブルースっていうのは自分に語りかけていると思うんです。生きる苦しさ、それは歌っても歌ってもなくなりはしない。だからまた歌うんだと思います。
僕は先にこのブルースと出会って、そこからゴスペルに出会っていきます。次回はそのゴスペルとブルースとの違いをお話したいと思います。
2014年の番組の再放送です。
Nobody knows the trouble I’ve seen.
Nobody knows the trouble I’ve seen, Nobody knows but Jesus
Glory hallelujah!
Sometimes I’m up, sometimes I’m down
Oh, yes, my Lord
Sometimes I’m almost to the ground
Oh, yes, my Lord
#2
この歌が黒人奴隷の深い悲しみを表しているスピリチュアルだということを前回お伝えしました。本当にこの曲は哀感に満ちた曲なんですね。
でもこの悲しみ、決してゴールではないんですね。そこに、究極のジャンプがある。この歌の中に悲しみだけじゃなくて、慰めと勝利がある。この歌は特にそれが生々しく、ビビットに描かれているなと思います。
Nobody knows But Jesus
大学生の時、僕は聖書もキリストも知らずに、初めてこの歌を歌った。その時、心に電流が走ったような感じがした。この「But Jesus」に不思議と心を掴まれた。きっと僕も、自分でも気づかずに大きな孤独と悲しみを胸に秘めて、この歌に出会ったんだと思います。
2014年の番組の再放送です。
#1
ゴスペルは日本で不思議な形で広まっています。
ゴスペルを歌う中で、黒人たちの魂の叫びに、心の深いところが震える。
そういう方がたくさんいるんですね。僕自身もそれを体験してきました。
僕が初めて出会った黒人霊歌「Nobody knows the trouble I’ve seen.(誰も知らない、私の悩みを。)」は、黒人霊歌の中でもSorrow song―「悲しみの歌」という分類に入る曲なんですけど、黒人霊歌っていうのはその底流に、奴隷体験という大きな悲しみの川が常に流れていると言えるんじゃないかなと思います。
2014年の番組の再放送です。

塩谷達也
ゴスペルシンガー、ソングライターとして、オリジナルゴスペルを歌い続けると共に、ゴスペルの「紹介者」としても活躍。ゴスペルクワイアの指導、著作活動、メディア出演など、その活動は多岐にわたる。現在、青山学院大学のコンテンポラリー礼拝においてワーシップディレクターを務め、学生賛美リーダーの育成に務めている。FEBCでは番組「Session―アートの中の彼の声」に出演中。
HP>>